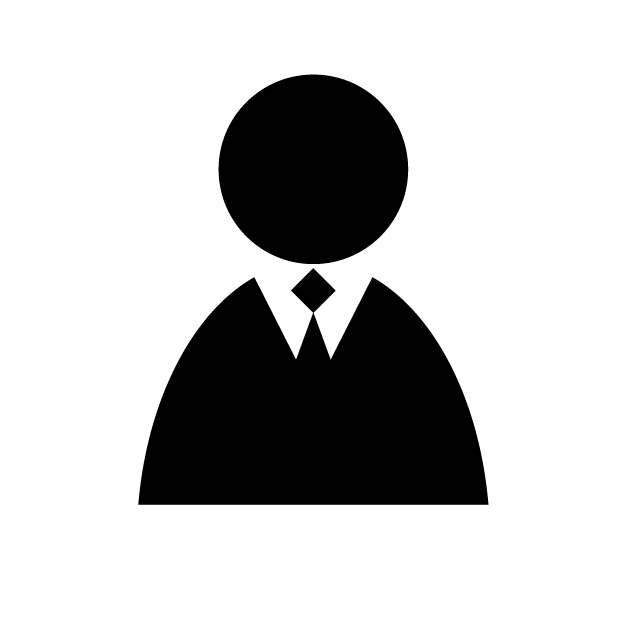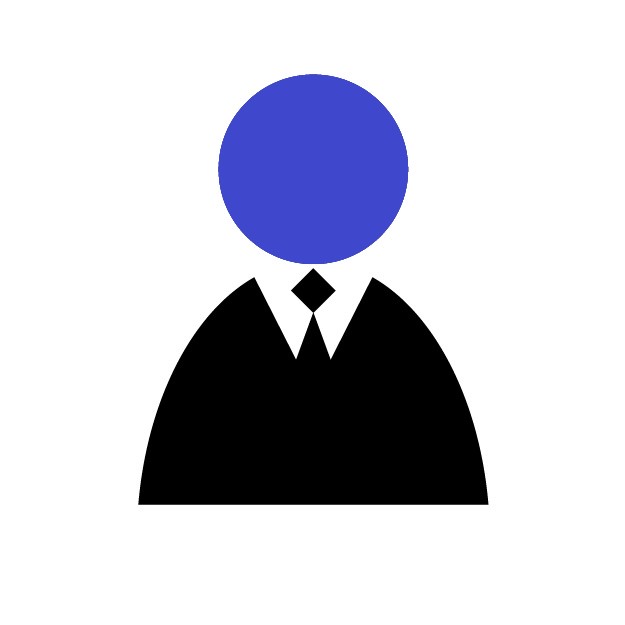お酒を飲むときに、欠かせないのが「あて」。
いわゆる「酒の肴」です。
「何も食べずにお酒だけを飲む」というのも良いのですが、食事をしながら飲むお酒はまた格別です。
では、お酒を飲むときの「肴」はどのように選ぶのが良いのかを考えてみたいと思います。
酒の肴はこう選ぶとよい
見た目で合わせる

ビールやワインなどの色のついたお酒は、色の薄いものから飲むとそれぞれの味の違いがよくわかるといわれます。
一般的に、色の濃淡が味の濃淡に比例するため、色の薄いものは端麗ですっきり、色の濃いものは芳醇でどっしりした味わいになります。
これを料理にも当てはめて、薄い色のお酒には薄い色の料理、濃い色のお酒には濃い色の料理を合わせると、大きく外すということはありません。
産地で合わせる

いろいろな国や産地でつくられるお酒は、その土地の料理に合うようにつくられているものが圧倒的多数。
広く言えば発祥国と合わせたり(ドイツビールにソーセージなど)、ワインや日本の地酒などで言えばその土地の郷土料理と合わせる、というのが間違いない選び方です。
味で合わせる

「見た目」で合わせることと似ているのですが、味わいで合わせるという方法もあります。
例えば、柑橘系の酸味がきいた食べ物にレモンのような爽やかな味の白ワイン、煮込みやバターなどのこってりした味にはコクのある濃厚な純米酒、など、味の方向性が似ているものを選べば失敗しません。
「ちょっとだけ違うな」というときは、調味料で近づけるという方法もあります。
あえて逆を選んでみる

上記の3つはいわばセオリー通りの選び方ですが、これはちょっとしたギャンブル要素も含んでいます。
例えば、「生牡蠣」。
「見た目」「産地」「味わい」ならば、ミネラル系の香りのする白ワインや爽やかな口当たりの吟醸酒などを選べば間違いないです。
そこで「ポーター」という色の濃いビールをあえて選ぶ、というような選び方。
特徴が全く違うもの同士ですが、お互いに無いものを補って引き立てあう組み合わせになります。
これ以外でも「極甘口ワインに塩辛い青カビチーズ」などが代表的な組合せです。
似ていないものを選ぶという事はむずかしいかもしれませんが、はまれば面白い選び方になるでしょう。

閑話休題。
お酒を飲んだら、塩分の濃いものが欲しくなったりします。
これは、体内の「カリウム」の濃度が上がるため。
ビールやワインには多くの「カリウム」が含まれています。
そして、人間の身体は「カリウム」と「ナトリウム」のバランスが悪くなると体調を崩してしまうのです。
なので、「カリウム」が増えると「ナトリウム」も増やさなければバランスが取れません。
この「ナトリウム」を多く含む食品が「塩」。
お酒を飲むと塩分が欲しくなる、というのは生理的には理にかなっています。
合う合わないとは
お酒と料理の相性というのは、いくつかパターンがあります。
- お酒と料理の相乗効果で風味が高まる
- お酒と料理に潜んでいた香りや味わいを引き出し合い、第3の風味がつくり出される
- お酒が料理を引き立てる、または料理がお酒を引き立てる
- 口の中に残る油分をお酒が流してくれる
- お酒が料理のいやな臭みを消して、隠れた風味を引き出してくれる
- 味の濃い料理をさっぱりさせてくれて、わかりやすくしてくれる
こういった場合はお酒と料理の相性が良く、「合う」ということ。
逆に、お酒と料理のバランスが悪くおいしい風味や特徴を消してしまう、お互いがあわさることによって不快な舌触りや感触を生み出す、お互いの欠点を引き出しあってしまう、といった場合は「合わない」ということになります。
一般的に「酸味」と「苦み」と「辛み」はお互いに合わせづらいですので、覚えておくといざというときに使えます。
誰でも知っている究極の選び方
つらつらとここまで書いてきましたが、じつは誰でも知っている究極の選び方というのが存在します。
それは、
「その時に食べたいものと飲みたいものを合わせる」
です。
でもこれは「お酒も料理も知っているもの同士」でこそ成り立つ選び方になります。
では「知らないもの」ならどうなのか?
そういう時に、先ほど書いた通り色や産地で合わせてみると失敗は少ないです。
知らないもの同士を組み合わせる、というのが実は一番楽しかったりします。
失敗も経験のうち。
いろいろと試してみて、良い相性を見つけてみてください。
ざこばの朝市公式オンラインショップ
![]()
創業85年京都ニシダやのお真心を込めて漬け込んだ伝統の味【京つけもの ニシダや】